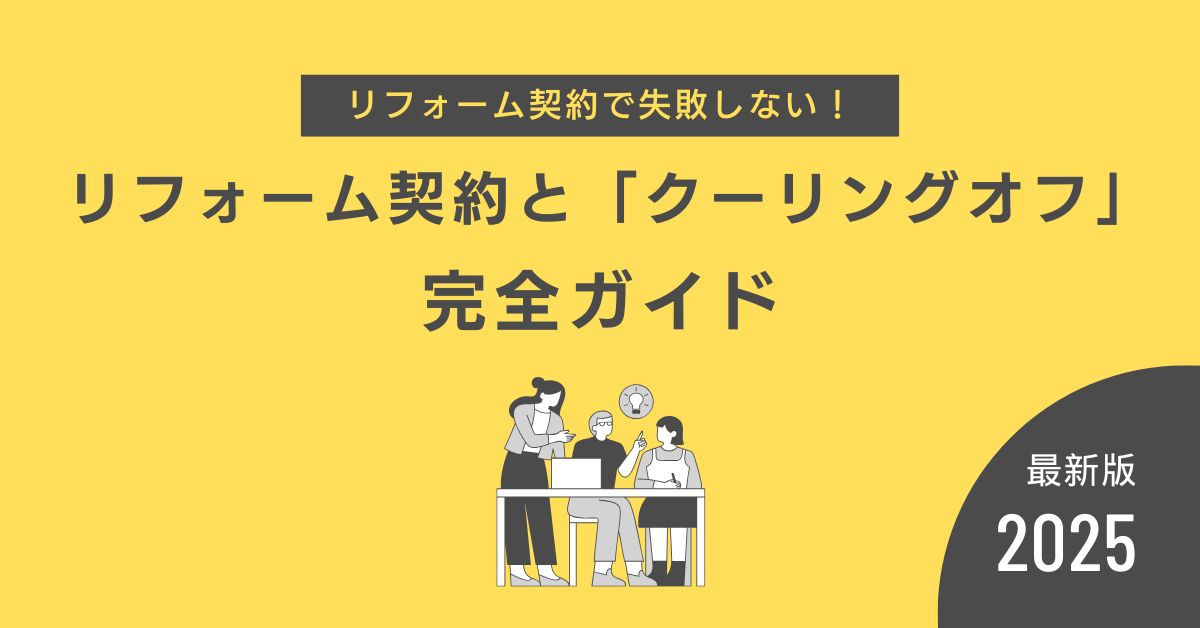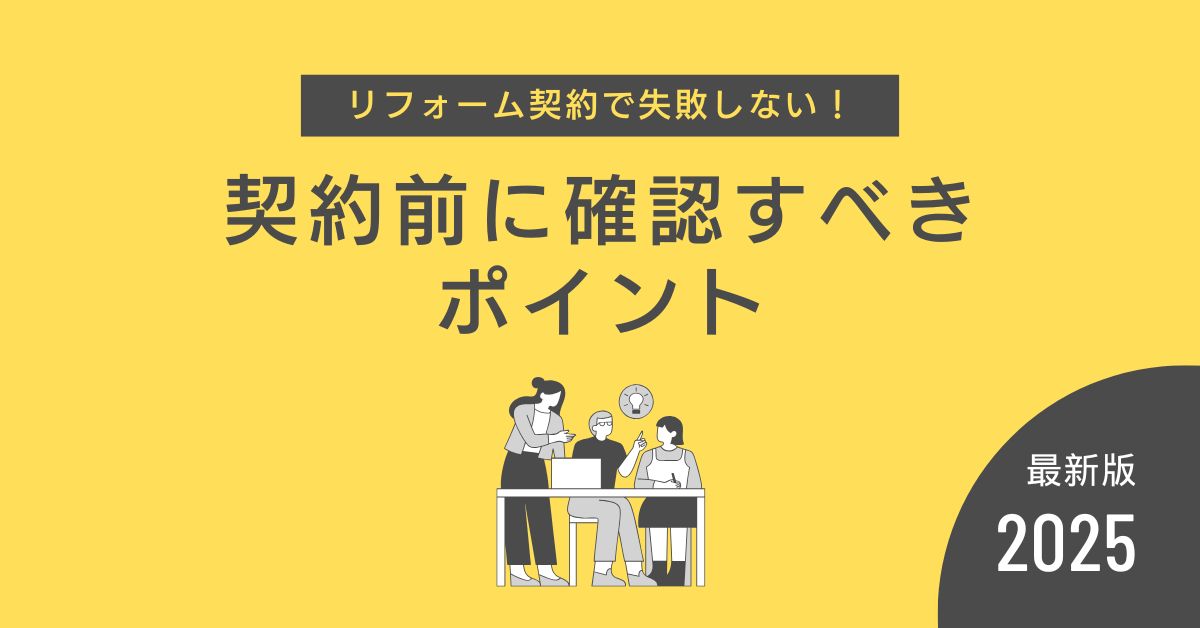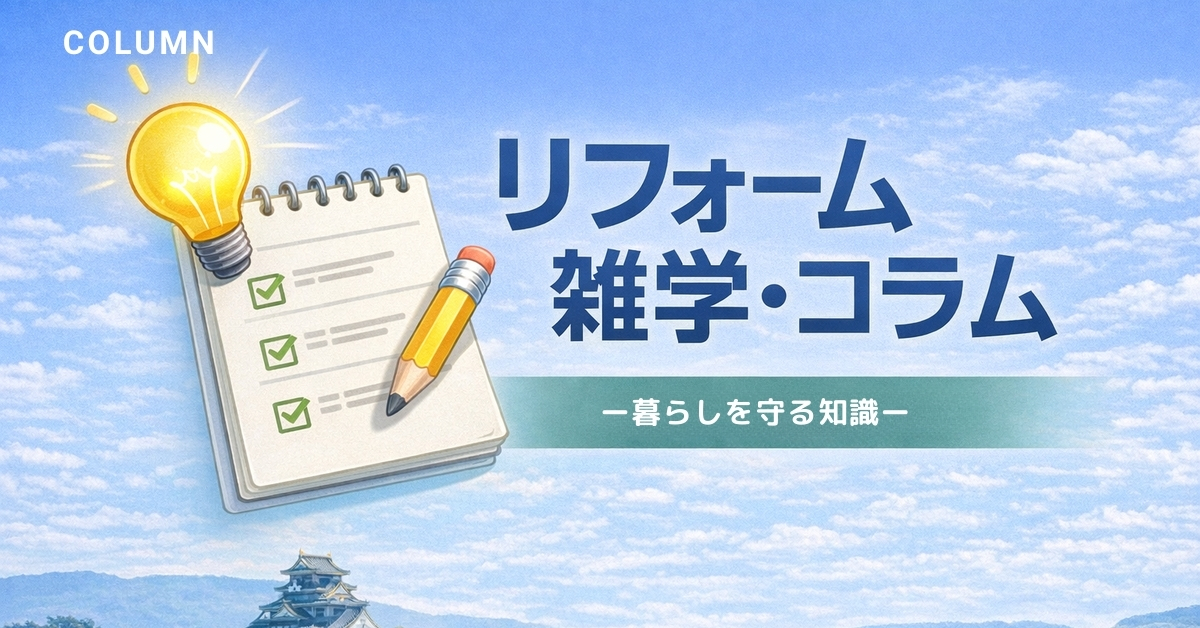リフォーム契約の「印紙代」完全ガイド|2027年3月までの軽減税額×電子契約で0円にする手順
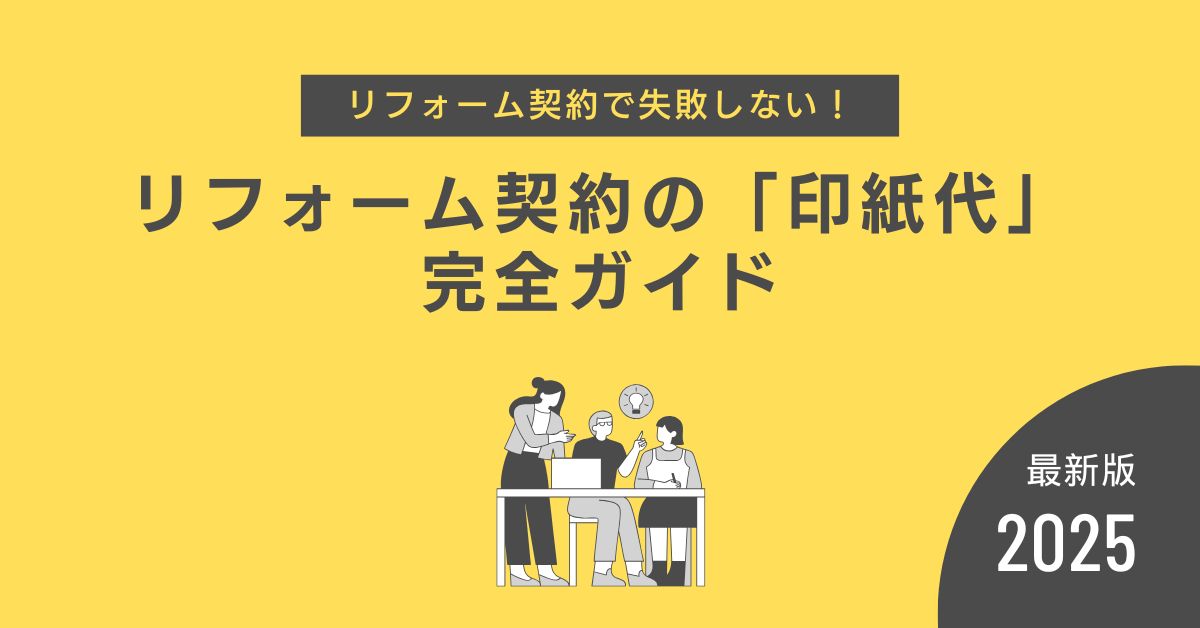
最終更新 2025-09-09
「本記事は一般的情報であり税務アドバイスではありません。最終判断は国税庁一次情報と税理士等の専門家に確認をお願いします」
「建設工事の請負に関する契約書」のうち一定の要件に該当する契約書の印紙税は軽減措置が2027/3/31まで延長されています。
本記事は2025年9月9日時点で公開されている国税庁資料に基づき整理しています。制度は更新され得るため、契約前に一次情報で最終確認を推奨します。国税庁
印紙代(印紙税)とは?施主・業者がまず押さえる基礎
印紙代=印紙税。リフォーム工事の請負契約書は第2号文書として契約金額に応じて課税されます。国税庁
リフォーム(=建設工事請負)は軽減措置の対象。2014/4/1〜2027/3/31作成分は税額が減税されています。国税庁
電子契約(電磁的記録)は原則非課税。紙で締結すると課税。途中で紙を別途交付すると、その紙は課税対象なので気を付けてください。国税庁
2通作るなら各通が課税対象(“写し・副本”でも成立証明目的なら課税)。国税庁
納税義務は作成者に成立。共同作成は全員が連帯して納付義務。国税庁
「第2号文書の要点」:なぜリフォーム契約に必要?
印紙税は、一定の取引に伴い作成される文書に課される国税です。請負契約書は印紙税額一覧表の第2号文書に該当し、契約金額に応じて税額が決まります(1万円未満は非課税/金額の記載がない契約書は200円)。国税庁
リフォームは「建設工事」の請負に当たり、のちほど述べる軽減措置の適用候補になります。国税庁
金額別の税額:一般税額と「建設工事の軽減」早見表
3-1. 一般(第2号文書)税額の要点(抜粋)
- 300万円超〜500万円以下:2,000円
- 500万円超〜1,000万円以下:10,000円
- 1,000万円超〜5,000万円以下:20,000円 など。国税庁
3-2. 建設工事請負の軽減税額(〜2027/3/31作成分)
- 300万円超〜500万円以下:1,000円
- 500万円超〜1,000万円以下:5,000円
- 1,000万円超〜5,000万円以下:10,000円
- 5,000万円超〜1億円以下:30,000円 など。国税庁
※100万円以下の契約は軽減対象外(一般税額の扱いに)。1万円未満は非課税。国税庁
| 契約金額(抜粋) | 一般(第2号文書) | 建設工事の軽減(〜2027/3/31作成) |
|---|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 | 対象外 |
| 1万以上~100万以下 | 200円 | 対象外(一般の扱い) |
| 100万超~200万以下 | 400円 | 200円 |
| 200万超〜300万以下 | 1,000円 | 500円 |
| 300万超〜500万以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万超~1,000万以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万超~5,000万以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万超~1億以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億超~5億以下 | 100,000円 | 60,000円 |
| 5億超~10億以下 | 200,000円 | 160,000円 |
| 10億超~50億以下 | 400,000円 | 320,000円 |
| 50億超 | 600,000円 | 480,000円 |
| 契約金額の記載なし | 200円 | (軽減規定なし) |
※1万円未満は非課税。100万円以下は軽減の対象外です。
(根拠:一般税額一覧表と軽減税額。国税庁)
※税込・税抜の記載で印紙税の「記載金額」が変わる場合、消費税額等を区分記載していれば
印紙税の記載金額に含めない。国税庁
電子契約なら原則ゼロ円になる理由と注意点
- 電磁的記録は“文書”に含まれないため、印紙税の課税対象外。よって電子契約(クラウド契約サービス等)で印紙代は不要。国税庁
- ただし、後日紙の現物を別途交付すれば、その紙の契約書は課税対象。運用ルールを社内・相手方と合わせる。国税庁
- 電子保存は電子帳簿保存法の要件も確認(運用・証跡)。国税庁
実務TIP:電子で合意→紙を「控え」で印刷するだけなら通常課税対象外ですが、「成立を証明する目的」で作る写し・副本は課税対象になり得ます。立て付けに注意。国税庁
電子契約のメリット:印紙代ゼロ、郵送・押印・保管の手間削減。国税庁
電子契約のデメリット:紙の別途交付は課税になり得る/保存要件(電子帳簿保存法)の運用整備が必要。国税庁
「誰が払う?」— 納税義務と通数の落とし穴 ー
- 印紙税は作成した時に作成者へ納税義務が成立。共同作成なら全員が各別に義務を負い、結局連帯して納める形に。国税庁
- 1つの契約で2通以上作る場合、それぞれが「契約成立を証明する目的」なら各通に印紙が必要(“副本”“写し”表記でも同様)。国税庁
まとめ:実務では「各当事者が自分の1通分を負担」or「工事代金に内包」のどちらか。契約前に明文化しておくのが安全。国税庁
お客様と業者、双方の視点で見る実務ポイント
6-1. お客様(施主)側
- 見積・契約前に「印紙代の負担者」「通数」「電子契約可否」を確認。
- 変更契約書(増減工事)も第2号文書に含まれ得るため、追加契約の都度の扱いを取り決める。契約金額を変更する契約書の記載金額については、変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかであるか否かにより、その取扱いが異なります。国税庁
- 電子契約が可能なら印紙代はゼロ。ただし保存・閲覧方法や担当者の操作手順もセットで確認。国税庁
6-2. 業者(施工店)側
- 軽減税額の適用要件(建設工事該当・作成年月日・金額区分)を理解しておくことが必要です。※軽減税額の期限は2027/3/31。国税庁
- 印紙税納付計器や書式表示(現金納付)を活用すれば、貼付の事務負担を下げられる。国税庁
- 電子契約に切り替える際は、紙の二重発行による課税リスクを回避。社内規程・運用フローを見直ししておく事。国税庁
よくある誤解とトラブル回避術
- 「1通だけ貼ればOK」は誤りになりがち。双方保存用に各通が課税文書として扱われれば各通に必要。国税庁
- 貼り忘れ・消印漏れは過怠税や追徴のリスク。チェックリスト化して押印・消印・保存まで一気通貫で管理。(実務通達・手引に基づく一般的注意)国税庁
- “写し”のつもりが課税対象になっていた、という事故を防ぐには「単なる控え」かどうかを文言と運用で明確にしておく事。国税庁
契約前チェックリスト(合意メモ・雛形)
税区分:第2号文書/建設工事の軽減(該当/非該当)
負担者:各当事者負担/施工店負担/工事代金内包
通数:2通/電子原本のみ(控えの扱い明記)
方式:電子契約(保存・閲覧・承認フロー)/紙(納付方法:印紙/納付計器/書式表示)
変更契約:増減が生じる場合の契約書作成・負担ルール。国税庁
FAQ(読者の疑問に実務で回答)
Q1. リフォーム(建設工事)の請負契約書、印紙はいくら?最短判定は?
第2号文書かを確認 → 記載金額の帯で判定 →(建設工事なら)軽減の可否(〜2027/3/31作成)を確認。
例:300万円ちょうどの建設工事請負契約書なら、一般1,000円/軽減500円。※軽減は100万円超が対象。消費税は区分記載があれば記載金額に含めない。 国税庁
Q2. 電子契約は本当に印紙0円?紙を後日渡したら?
**電磁的記録は「文書」に含まれないため原則非課税。ただし電子送信後に紙の現物を“別途交付”**すれば、その紙は課税対象。 国税庁
Q3. 注文書・注文請書を双方で作る/写し・副本は何通に貼る?誰が負担?
成立証明目的で作った写し・副本も課税。各通に貼付。納税義務は作成者、共同作成なら連帯納付。費用負担は当事者の合意で決めてOK(ただし税務上の義務は残る)。 国税庁
Q4. 追加・減額など“変更契約書”の印紙税は?
増額なら“増加額”が記載金額、減額なら“記載金額なし”。変更後金額しか書かれていない場合はその金額が記載金額。所属号は原契約の重要事項の変更に応じて判断。 国税庁
Q5. 貼り忘れ・消印漏れのペナルティは?
未貼付=3倍の過怠税。ただし自己申出(印紙税不納付事実申出書)が調査前なら1.1倍に軽減。消印漏れは額面相当の過怠税。 国税庁
まとめ
リフォーム工事の請負契約書は第2号文書で、金額に応じて課税。
建設工事の請負契約の印紙代軽減は〜2027/3/31まで有効。対象・金額帯を必ず確認。
電子契約なら印紙代は原則ゼロ。紙の別交付や写しの扱いに注意。国税庁
「本記事は一般的情報であり税務アドバイスではありません。最終判断は国税庁一次情報と税理士等の専門家に確認をお願いします」
参考URL(一次情報・国税庁中心)
- No.7140 印紙税額の一覧表(第2号文書ほか・一般税額)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm - No.7108 不動産・建設工事の軽減(〜2027/3/31作成分。第2号文書は100万円超から)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7108.htm - No.7124 消費税額等の区分記載の扱い(区分記載があれば消費税は記載金額に含めない)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7124.htm - No.7120 写し・副本でも成立証明目的なら課税/各通貼付
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7120.htm - 質疑応答「電磁的記録は文書に含まれない」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/02/10.htm - 福岡国税局 文書回答(電子送信後に紙を別途交付すると課税)
https://www.nta.go.jp/about/organization/fukuoka/bunshokaito/inshi_sonota/081024/02.htm - No.7123 変更契約書の記載金額(増額=増加額/減額=記載金額なし/変更後金額のみ=その金額)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7123.htm - No.7127 変更契約書の所属号(原契約の重要事項の変更に応じて判断)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7127.htm - No.7131 過怠税(3倍/自己申出1.1倍/消印漏れ=額面相当)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7131.htm
この記事の著者

<名前 / Name>
リフォームBlog代表よしのり
<実績 / Achievements>
20年間大手ハウスメーカーのリフォーム部門で営業・設計・現場管理を学ぶ。営業所長・エリアマネージャーを歴任。累計100棟以上の住宅リノベーションを担当し、現在は地元で地域密着リフォームを実践しています。最新のリフォームの情報やノウハウをブログで公開します。 <資格 / Qualifications & Certifications>
二級建築士・二級建築施工管理技士・既存住宅状況調査技術者・古民家鑑定士一級・外装劣化診断士